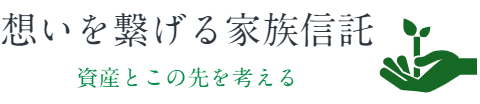家族信託は、親の老後や認知症対策として注目されている制度ですが、すべての財産を信託できるわけではありません。制度をうまく活用するためには、「信託できない財産」の種類についてあらかじめ理解しておくことが大切です。本コラムでは、信託できない財産を解説します。
たとえば、年金は代表的な「信託できない財産」のひとつです。公的年金は個人に直接支給されるものであり、受給権を第三者に譲渡したり、信託の対象としたりすることは法律上認められていません。親の年金で生活費をまかなおうとしても、その管理はあくまで本人名義で行う必要があります。
同様に、生命保険契約の「契約者の地位」も信託の対象外です。たとえば、親が自分を契約者として加入している生命保険を、そのまま家族信託に移そうとしても、契約者の地位は移転できません。保険金の受取人が誰であっても、契約者の権利は引き継げないため、別の対策が必要になります。
また、祭祀財産、お墓や仏壇なども信託できない財産に含まれます。これらは民法で祭祀承継者に引き継がれるべきとされており、金銭的価値ではなく精神的な意味合いを持つ財産だからです。家族信託では扱えないため、遺言や家族会議などで引き継ぎについて話し合うことが現実的でしょう。
さらに、借金や連帯保証といった「債務」も信託には含められません。たとえば、親が抱えるローンを家族信託でまとめて管理したいと考えても、それはできません。債務は原則として信託できず、借入先と個別に対応する必要があります。
このように、家族信託で信託できる財産には制限があります。土地や建物、預金などは比較的スムーズに信託できますが、制度上制限されている種類の財産も存在するため、事前の確認が重要です。誤った理解のまま契約を進めると、後々トラブルの原因にもなりかねません。信託できるもの・できないものの線引きをしっかりと把握し、制度の限界も踏まえたうえで専門家と連携して計画を立てましょう。