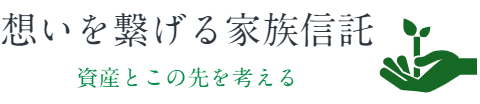家族信託は、高齢の親の財産管理や相続対策として注目されている制度ですが、その設計や運用を誤ると、親族間で思わぬトラブルに発展することがあります。制度を安心して活用するには、信託を始める前からトラブルの芽を摘んでおく防止策が欠かせません。本コラムでは、家族信託によるトラブル防止について解説します。
トラブルの原因としてよくあるのが、「信託の内容を他の親族に説明していない」というケースです。たとえば、長男を受託者として信託契約を結び、不動産や預金の管理を任せたとします。本人たちは合意していたとしても、他の兄弟姉妹に説明がなければ「なぜ長男だけが財産を動かしているのか」「自分は何も知らされていない」と不信感が生まれやすくなります。
こうした親族間の不信を避けるには、信託契約を結ぶ前の段階で、関係する家族全員に制度の仕組みと目的をしっかり説明し、共有することが重要です。特に、受益者が複数いる場合や、最終的に相続へつながる財産を扱う場合は、透明性が信頼関係を守るカギとなります。
また、受託者の判断で財産の使い道が大きく変わる場面では、客観的な記録を残す工夫も有効です。たとえば、定期的な報告書を作成し、他の親族にも閲覧できる形にしておくことで、「何に使われたか分からない」といった疑念を減らすことができます。メールや共有フォルダでの報告も、トラブルの予防に役立ちます。
さらに、信託契約そのものに「監督人」や「指図権者」といった役割を設けることも検討に値します。たとえば、長男が受託者、長女が監督人という形にすれば、財産管理に第三者的な視点が入り、バランスを取りやすくなります。監督人がいれば、受託者も一方的な判断を避け、責任ある行動が求められるため、制度の健全な運用につながります。
家族信託は資産管理に有効な制度ですが、親族間でのトラブルが起きやすい点には注意が必要です。特に契約内容の共有不足や、受託者の行動が不透明な場合には、不信感が生じやすくなります。事前の情報共有や定期的な報告、監督人の設置といった防止策を講じることで、親族間の信頼関係を保ち、トラブルの発生を抑えることができます。制度のメリットを活かすには、家族全体での理解と合意形成が不可欠です。